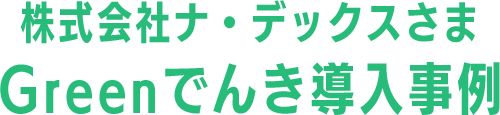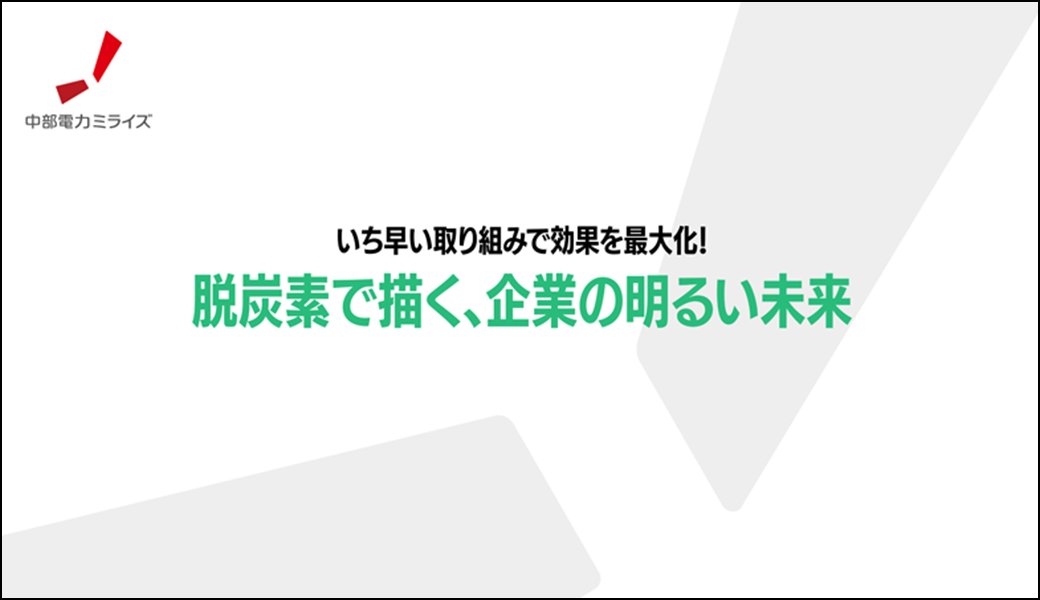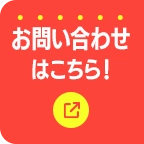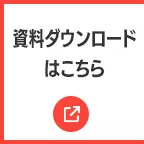初代プリウスをきっかけに、環境問題への意識が芽生えた
毛利さん御社が環境への取り組みをスタートされたのはいつ頃ですか?
大澤さんこれはハッキリ覚えています。1997年に初代プリウスが発売されたときですね。といっても当時は環境意識が高かった訳ではなく、今思えばそれが環境への取り組みをスタートするきっかけだったなと考えています。
当時は環境意識というより、1リットルあたり28kmという燃費性能に惹かれて、社用車にプリウスを採用しました。
野池さん毛利さんはまだ生まれていなかったと思いますが、当時のプリウスのキャッチコピーは「21世紀に間に合いました」というものでしたね。化石燃料依存からの脱却という車の未来そのものでした。
大澤さんハイブリッド車はガソリン車の2倍の燃費性能ということで、しばらく経つと毎月のガソリン代が大幅に減るという効果が得られました。それはそれで嬉しかったのですが、私たちが低燃費車に乗り換える行為自体も、世界規模のCO2削減に微力ながら貢献していたのだとずいぶん後になって気付きました。
毛利さん他社製品の購入を通じて、環境意識が芽生えるというのは中々おもしろいですね。
野池さん一度気付いてしまったからには、その後さらに環境問題に貢献したいという思いがふつふつと湧いてきて、社内で節電や節水を呼びかけ、全社員の意識を高めることに挑戦しました。
大澤さんでも社員に無理があっては長続きしないので、無理なく環境問題への意識を高めてもらうため、まずは「不要な照明は消しましょう」ですとか「健康のために階段を使いましょう」など、身近な活動からはじめました。
毛利さん成果はいかがでしたか?
大澤さん電気料金や水道料金としての効果はわずかなものでしたが、社員の環境に対する意識の芽生えには役立ったのかなと感じました。
毛利さんその後はどんなことに取り組みましたか?
野池さん理想としては、普段通り仕事をしながらも環境問題にしっかり貢献できること。そのために電力の使用量をモニタリングするデマンドコントローラーや、電力損失を減少させる力率改善用機器などを導入しました。
大澤さんさらにエアコンには制御装置を取り付けて30分ごとに自動で送風運転になるようにしたり、照明をLEDに交換したりと、気付いたことからすぐ行動に移していきました。しかし、それらの活動をすべて合わせても、CO2削減を当社の強みとしきれないというモヤモヤを抱えていました。
毛利さんそれはなぜですか?
野池さん商社という当社のビジネスモデルからです。製造業であれば、CO2削減に取り組んだモノづくりで優位性を獲得できるのですが、商社である我々が排出するCO2はオフィスで使用する電力と社用車のガソリンくらい。すでに社用車はハイブリッド車に切り替えていたため、それ以上にできることが見当たらず、大きな壁にぶつかってしまったのです。
大澤さんそんな中、2021年度を始期とする中期経営計画の策定にあたり、基本姿勢としてESG経営を盛り込むことに。改めて当社が使用する電力量を調べ、当時の取り組みからどの程度CO2削減に貢献しているのか詳しくシミュレーションしました。
野池さんこれが脱炭素に向けたリスタートのきっかけとなり、役員含め全社員が一丸となり環境問題に取り組む企業に生まれ変わったと感じています。
毛利さん2024年5月に「Greenでんき」を導入したきっかけを教えてください。
野池さん2024年に新中期経営計画を策定したのですが、その際、CO2削減のシミュレーションを改めて見直しました。
大澤さん国内拠点だけでなく海外拠点に対してもシミュレーションをもとに、より精緻な数字に落とし込むことで、2030年、2050年までにどの程度CO2を削減できるのか指標を明確にしたのです。
野池さんそんなとき、中部電力ミライズの担当者さまから提案いただいたのが「Greenでんき」でした。
毛利さんそれ以前に「Greenでんき」はご存じでしたか?
大澤さんテレビのCMを見たことはあるのですが、詳細は知りませんでした。
野池さん中部電力ミライズの担当者さまから、非常に丁寧に説明いただき、これであれば確実にCO2削減を実現できると実感しました。ただ、購入にはハードルもあるなと感じていました。
大澤さんハードルというのは、“コスト面における不安”でした。ウェブで脱炭素の電気を検索すると、中々しびれる金額のところが多くて。
毛利さんその不安はどのように払拭されたのですか?
大澤さん後日、担当者さまから分かりやすくまとめられた試算をいただいたところ、実は想像していたコストより低く抑えられていたのです。
野池さんその試算をもとに稟議資料を作成し取締役会で提案したところ、すぐに導入が決定しました。
大澤さん割合についても最初から100%を選択すると決まり、本社および北名古屋市にある技術センターの2ヶ所に導入しました。
野池さん今後は、社内外へのアピールのため、当社のホームページと会社案内に「Greenでんき」のロゴと証明書を掲載する予定です。
大澤さん導入して数ヶ月のためまだ大きな変化は見られませんが、取引先企業さまからいただくアンケートにCO2排出係数ゼロと返答できるようになったことは、大きなメリットです。
野池さん当社の溶接制御機器は、自動車の溶接プロセスにおけるエネルギー消費を最小限に抑え、CO2の排出量を減らすものなのですが、それだけでは購入していただけない時代が来ると感じています。
大澤さん近年は自動車産業をはじめCO2削減の取り組みが急速に進み、我々サプライヤーについてもCO2排出量の削減目標が要請されており、サプライヤーとして選ばれ続けるためには、脱炭素への取り組みは重要なパスポートとなるのです。
毛利さん最後に、脱炭素社会の実現に貢献するため、さまざまな取り組みを検討していらっしゃる中小企業の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
大澤さん脱炭素への取り組みにあたって投資は必要ですが、近い将来に事業継続&取引先拡大という果実が実るはずです。その中でも、中部電力ミライズの「Greenでんき」については、比較的低価格かつスピーディーに取り組めますし、そのコストも一部が再生可能エネルギー事業の促進に充てられているというのも、環境問題に貢献している感じがして気分がいいものですよ。
野池さん当社もそうでしたが、まずは節電や節水など身近なことに取り組み、社員が一丸となって環境への意識を高めること。「Greenでんき」はそんな最初の一歩としてもおすすめできるものです。私は家族から「いい会社だね」と褒めてもらうのが、大きなよろこびになっています。
毛利さんそれはうれしいですね!すてきなお話をありがとうございました。