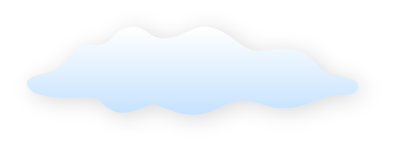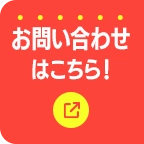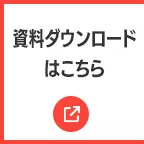Story
07
炭素会計4つ目のステップ:
「情報開示」とは?

第5~6回のコラムでは、炭素会計(カーボンアカウンティング)における(1)現状把握、(2)目標設定、(3)削減の実施について解説してきました。そして次のステップが、これらの取り組みを(4)情報開示することです。以後は(1)~(4)のステップを繰り返しながら、ビジネスの持続と成長を目指していくことが、これからすべての企業に求められています。この道のりには、すでに多くの企業が先行して取り組み、実践的な“道しるべ”を示してくれています。今回は、そうした情報開示の動きを紹介しながら、これまでのコラムの流れを振り返ってみましょう。
今回のコラムで学べること
- 情報開示の意義と企業経営における重要性
- CDPとTCFDが示す国際的な開示の枠組み
- 連載の総括から見える脱炭素経営の実践ポイント
Chapter 01 情報開示の意義と企業経営における重要性
情報開示とは。
情報開示がもたらす価値
「情報開示」とは、単に数字を並べて目標や成果を示すだけではありません。それは脱炭素に向けた経営姿勢の表明であり、企業としての意思の発信という側面を持っています。トップがコミットした適切な情報開示によって、事業活動への評価と信頼が高まり、新たなビジネス機会の創出や持続的な経営、さらには社会への貢献へとつながっていくのです。

この情報開示に関する世界のトレンドを見ていきましょう。企業活動における脱炭素の情報開示を世界的に推進しているのが、「非国家アクター」と呼ばれる存在。これは国連や政府ではなく、民間の団体や企業、投資家の集まりによって主導される取り組みを指します。前回ご紹介した「SBT」や、企業の使用電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す国際イニシアティブ「RE100」もその一例でしょう。彼らは国家や政府による補助制度や規制とは異なるアプローチで、世界の脱炭素を牽引してきました。
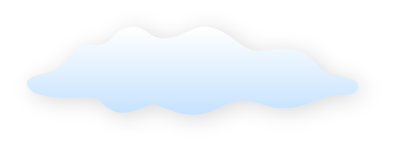

情報開示は社会や投資家への情報提供、さらには業界内や他社との比較を通じて、脱炭素への大きな推進力を生み出しています。これを主導する代表的な存在が、次にご紹介する「CDP」と「TCFD」です。
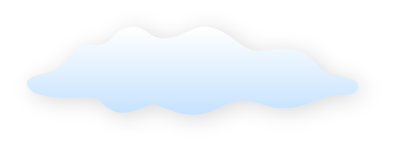
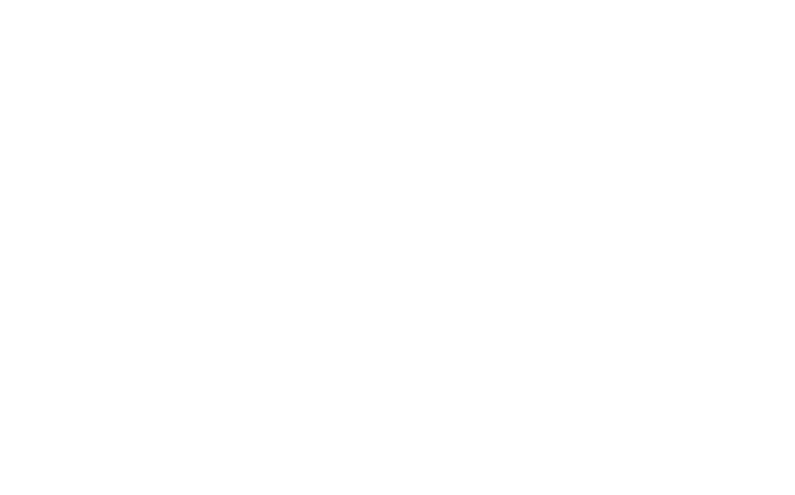
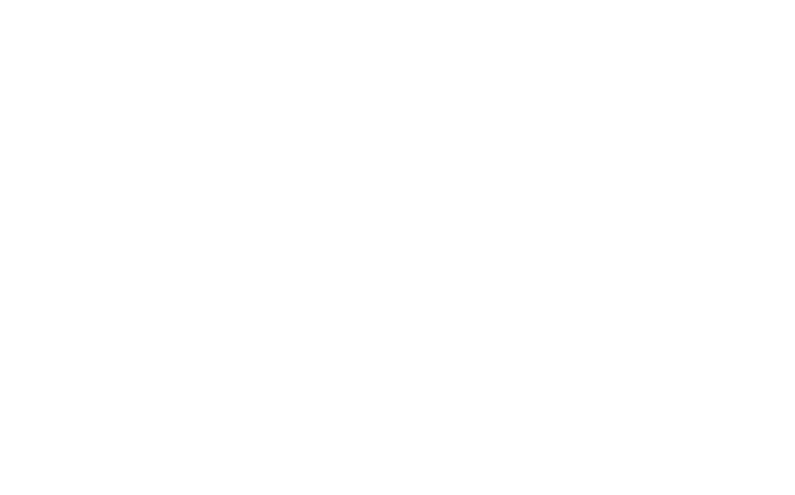
Chapter 02 CDPとTCFDが示す国際的な開示の枠組み
国際的な情報開示の枠組み。
CDPとTCFDが示す新たな潮流
CDPは英国に本拠を置くNGO(非政府組織)として2000年から活動を展開しています。元々はカーボン・ディスクロージャー・プロジェクトの略称でしたが、現在は“シー・ディー・ピー”というアルファベットの読み方が正式名称となっています。CDPの特徴は、温室効果ガスの排出量や削減目標・対策に関して企業へ質問し、その回答を取りまとめて公開するという、シンプルかつ継続的な取り組み。その際「スコアリング」と呼ばれる格付けをおこない、投資家の判断材料として活用されています。この毎年の取り組みが、事業者の排出量削減を着実に促進してきました。

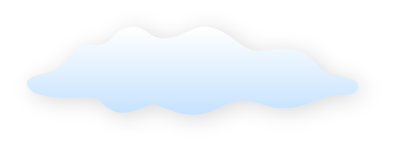
対象は企業にとどまらず、都市や自治体といった行政機関も含め、全世界で約2万の組織が情報開示を実施。日本でも2022年から東証プライム上場企業約2000社全てが回答対象となり、日本のオフィス「一般社団法人 CDP Worldwide-Japan」が企業の取り組みをサポートしながら、様々なガイダンス資料を提供しています。

一方、TCFDは2015年のパリ協定採択後、金融業界主導で設立された気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial
Disclosures)です。スイスに本部を構え、「企業が気候変動から受けるリスク」や「対策投資の財務的影響」を明らかにすることを目指してきました。統一された基準での情報開示を通じて投資家に判断材料を提供し、財務面から企業の脱炭素への取り組みを促進する役割を担っています。
その影響力は着実に広がり、2023年9月現在、世界全体では金融機関をはじめ4831の企業・機関が賛同を表明。特に日本は1454の企業・機関が参加し、世界最多となっています。現在TCFDは組織としては解散していますが、そのフレームワークは引き続き多くの企業で活用され、その重要性はさらに高まっているのです。

これらCDPとTCFDは、いずれも事業者が自らの意思で参加する自己宣言・自己申告型のプラットフォーム。参加しないことへのペナルティはありませんが、社会や投資家の評価軸として機能することで、企業の成長機会の創出とリスク回避に寄与する役割を担っているのです。
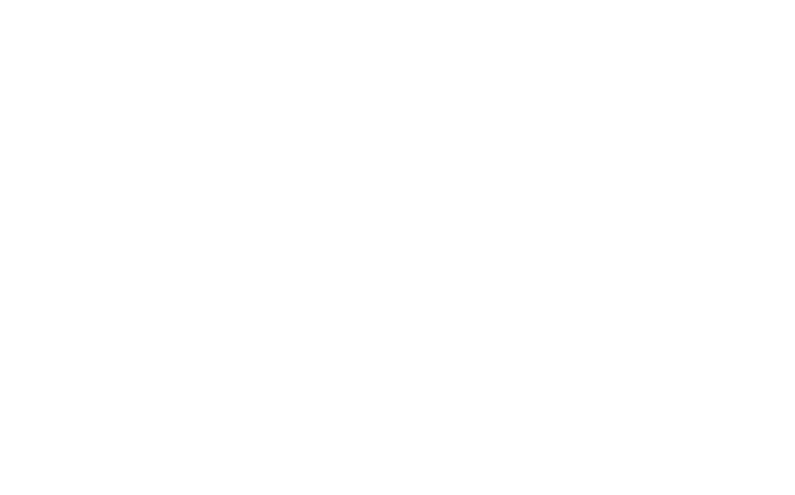
Chapter 03 連載の総括から見える脱炭素経営の実践ポイント
連載の学びを活かして。
これからの一歩を踏み出すために
これまで7回のコラムを通じて、私たちが向かう脱炭素社会への道筋を探ってきました。その過程で見えてきたのは、毎年進化を続ける世界の潮流と、それに呼応する日本の動きです。サイエンスが示す目標に向けて、ビジネスが本格的に動き出すことで生まれた大きなうねり。そしてその成否を握る地域での取り組み。さらには事業者による炭素会計の実践まで、様々な視点から解説を重ねてきました。

事業活動には必ず温室効果ガスの排出が伴います。その量の多少に関わらず、来るべき時代へと事業を継続していくためには、国家および国家以外のルールメーカー含めた国内外の動きに沿った排出削減と情報開示の取り組みが不可欠でしょう。まず現状を把握し、目標を定め、具体的な対策を選択する。この基本的なステップなくして、効果的な管理は望めません。そして、リスクと機会を見極め、財務との関わりを理解し、それらを経営戦略に反映させることが重要です。この取り組みを公開することで社会からの評価を得て、次の時代を切り拓くチャンスが広がっていく。その第一歩を、皆様に踏み出していただきたいと願っています。
この連載が、皆様の次の一歩を踏み出すためのヒントとなれば幸いです。