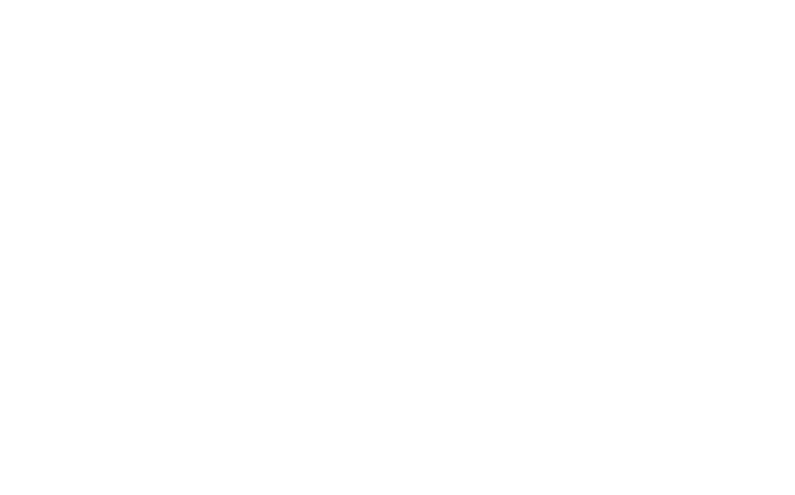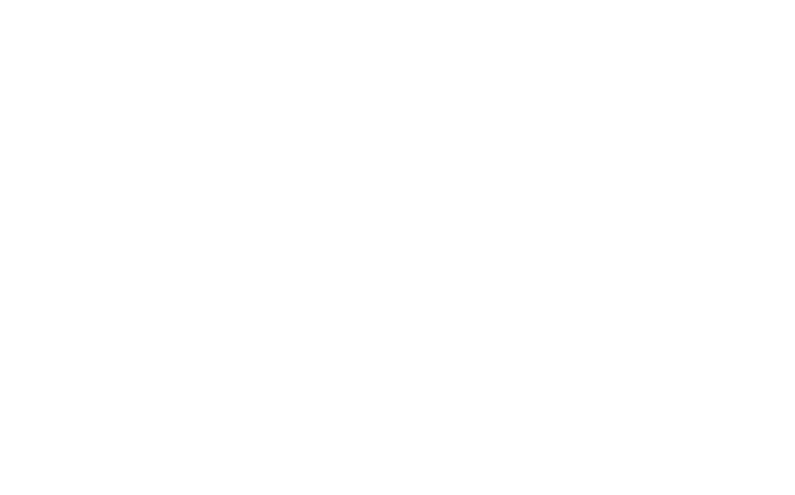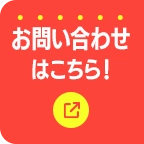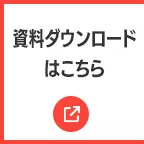Story
05
脱炭素への道を着実に一歩ずつ。
炭素会計で実践する排出量の把握

「脱炭素に向けて何から始めればよいのか?」。これは多くの企業が直面している課題ではないでしょうか。その第一歩として重要なのが、自社のCO2排出量を正確に把握すること。ここでは、そのための実践的な方法である「炭素会計(カーボンアカウンティング)」について、基礎から具体的な進め方までご紹介します。
今回のコラムで学べること
- 炭素会計の4つの基本プロセスと進め方
- 排出量の具体的な算定方法とScope1〜3の考え方
- サプライチェーン連携による脱炭素の実現方法
Chapter 01 炭素会計の4つの基本プロセスと進め方
炭素会計の基本プロセス。
現状把握から情報開示まで
炭素会計は、事業活動による二酸化炭素の排出を削減していくための体系的なアプローチといえます。具体的には、以下の4つのプロセスで展開していきます。

(1)現状把握:事業活動から直接・間接に排出される二酸化炭素などの排出量を計算する。
(2)目標設定:パリ協定で合意したネットゼロ社会に向けた国際水準に合った削減目標や取引先の要請など、自社が達成すべき目標を設定する。
(3)削減の実施:省エネや再生可能エネルギー導入のほか、低炭素製品・サービスの調達、環境に配慮した製品開発などの削減活動を実践する。
(4)情報開示:これらの取り組みを情報公開し、投資家や社会に向けて発信する。
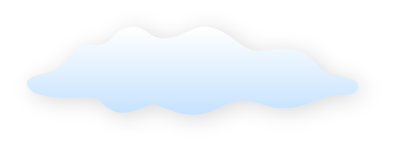

排出量の算定方法。
財務会計との連携がポイント
事業活動に伴う排出量の算出には、単位活動量当たりの排出量を示す「排出係数」や「排出原単位」と呼ばれる基準値を活用。これらの数値と実際の活動量を掛け合わせることで、二酸化炭素などの排出量が算定できます。
活動量の数値は、生産量・使用料・輸送量・処理量など、財務会計に記録されている数値と整合させることが望ましいでしょう。これにより、財務との関連性が可視化され、より実践的な管理が可能となります。また、使用する原単位については、後述する国際基準や国・業界がまとめたデータを参考にしていきます。
こうした排出量の現状把握においては、2つの重要な視点があります。1つはサプライチェーンの観点から、もう1つは排出原単位に用いるデータの選択です。
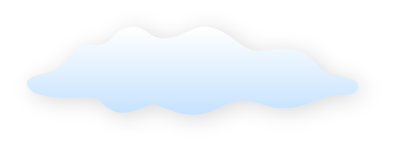
Chapter 02 排出量の具体的な算定方法とScope1〜3の考え方
Scopeの基本的な考え方。
サプライチェーン全体での排出量把握
企業の温室効果ガス排出は、その発生源によって3つのScope(範囲)に分類できます。この分類により、自社の直接的な活動だけでなく、取引先との関係性まで含めた包括的な把握が可能となっているのです。

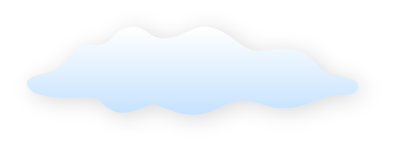
まず、Scope1は企業活動による直接的な排出を指します。具体的には、燃料の燃焼など、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出が該当するでしょう。次にScope2は、他社から供給された電気・熱・蒸気などの使用に伴う間接排出。そしてScope3は、事業活動の上流と下流における活動による排出を対象としています。

Scope3の範囲は広く、上流では他社による原料調達、部品製造、輸送、リースなどが含まれ、下流では販売した製品の使用やサービス、廃棄までを対象としているのです。これら3つのScopeを総合的に把握することで、原料調達から使用・廃棄に至るまでのサプライチェーン全体の排出量が明らかとなります。
サプライチェーン全体での排出量把握は、自社の敷地内の活動だけでなく、他社との関わりまで含める必要があり、一見すると手間のかかる作業に思えるでしょう。しかし、ガイドラインによって具体的な考え方や計算方法が示されており、これに従うことで効率的な進め方が可能となっているのです。

特にScope3は他社の事業活動による排出を対象とするため、必ずしも手元にデータがない場合も。その際は、関係する取引先から排出量データの提供を受ける方法と、活動量のデータを得て「活動量×排出原単位=排出量」という計算をおこなう方法の2通りから選択することができます。
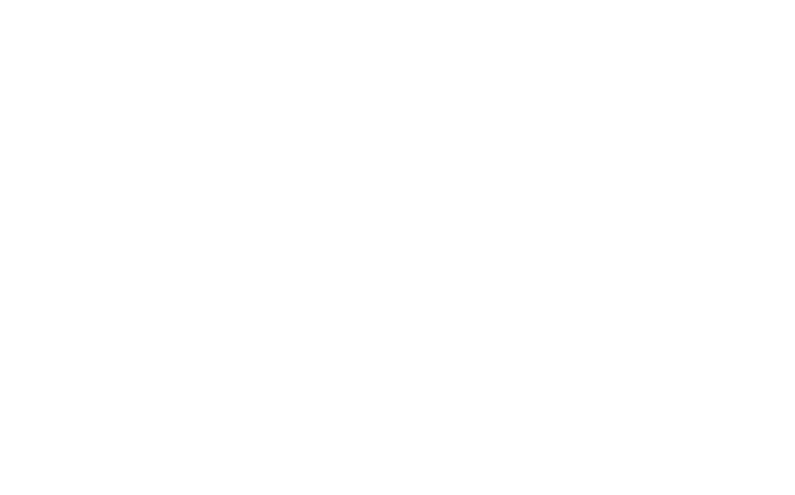
Chapter 03 サプライチェーン連携による脱炭素の実現方法
国際標準と国内指針。
実務に活かす算定ガイドライン
排出量の算定には、2つの重要なガイドラインが存在します。米国の環境NGOが中心となってまとめた国際基準「GHGプロトコル」と、環境省・経済産業省がまとめた国内指針です。

GHGプロトコルは、WRI(世界資源研究所:World Resources Institute)とWBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議:World
Business
Council
for Sustainable Development)が中心となってまとめた国際的な算定・報告基準。
ここにはGHG(温室効果ガス:Greenhouse
Gas)の算定と報告基準、計算方法のガイダンス、排出原単位データ、計算ツールなどが体系的に示されています。先に説明したScope1~3の考え方も、このプロトコルの中で定義付けられています。
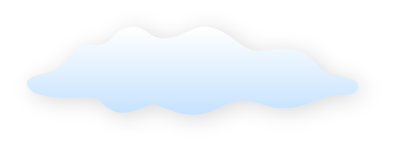


一方、日本では環境省と経済産業省が「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を作成。併せて「排出原単位データベース」も公表されており、国内事業者の実情に合わせた算定が可能となっています。特に、これから排出量の算定を始める企業にとっては、この国内ガイドラインが実践的な道しるべとなるでしょう。
サプライチェーンでの連携がもたらす価値。
脱炭素と企業成長の両立
サプライチェーン全体での排出量把握は、関係事業者との脱炭素に向けた連携と相互の学び合いの機会となります。上流の事業者が排出削減した分は、下流の事業者の削減分として計上することができ、互いに負担を軽減し支援し合うことにつながっているのです。
これらの連携と相互支援は、単に炭素会計を円滑に進めるだけではありません。むしろ自社のビジネスの未来にとってもプラスとなるでしょう。そしてサプライチェーン全体に目を向けることこそ、自社と社会のサステナビリティの第一歩となり、その結果として地域全体の脱炭素に貢献することになるのです。
あなたの会社でも、まずは炭素会計から第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。